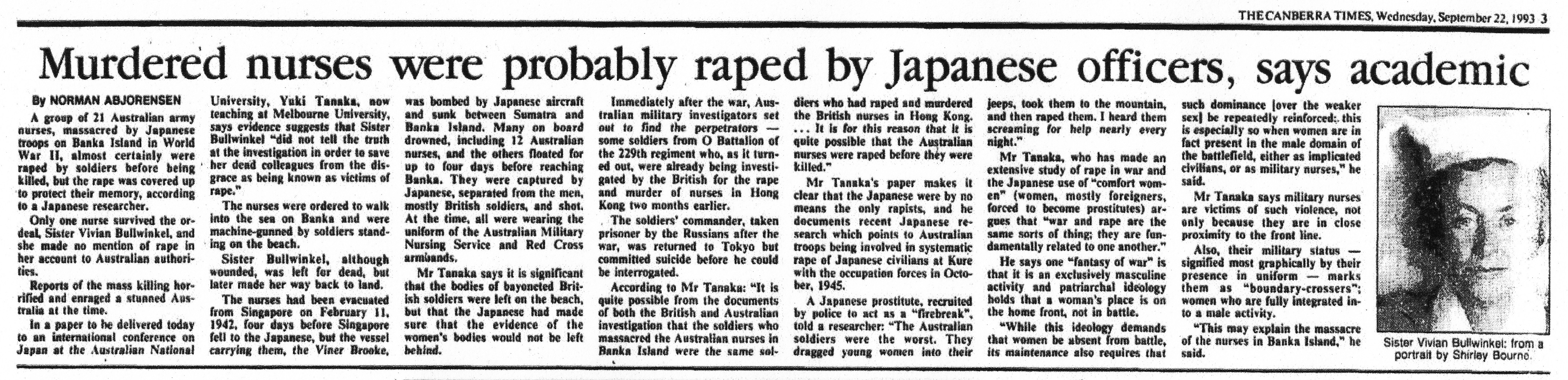(1) 大体の事実経過
この「事件」については既にご存知の方、びっくりされた方も多いと思うが、未だ混乱が収束したと言う状況ではないこの時期(2019年8月現在)に、あえてこれまでの経過と事件の内容・本質について、本ブログ(アカデミックハラスメント情報資料室)の関係者でDAYS JAPAN の一読者の立場から、出来る範囲でまとめ、コメントを試みたい。
まずおおざっぱな事実経過は次のようなものであろうかと思われる(細かい点は正確でない可能性有り)。
2018/12/26 この日発売の「週刊文春」19年1月3日・10日号は、広河隆一氏(*1)が事実上主宰していた雑誌DAYS JAPAN (*2) の元ボランティア等7人の女性達による、広河氏の10年に渡る性暴力・セクハラ被害の証言 (*3) を掲載・告発。
同日、広河氏自身から短いコメント(*4)が出され、またDAYS JAPAN発行元((株)デイズジャパン)からもコメント (*5) が発表された。
デイズジャパン社からのコメントでは「広河氏が被害者の方々の尊厳を傷つけてしまった」と詫び、広河氏の代表取締役等からの解任を報告している。また「弊社として、広河氏の言説を看過するわけにはいかず、これに与する立場ではない」として、本人に今後の誠実な対応を求めると同時に雑誌刊行への取り組みの意志を示している。
2018/12/31 (株)デイズジャパンより2回目のコメント(6*)。事件の検証をDAYS最終号(もともと3月末で休刊予定)で公表すると表明。
この声明では、上記7名以外にも「性暴力」被害者がいたこと、「性暴力」とは別に社員・協力スタッフに対するパワハラともいわれる事例があったことなどを認め(度々の問題提起に対し会社として真摯な対応をして来なかったが)、具体的に踏み込んだ内容となっている。今後については(責任者を入れ替え?)引き続き広河氏個人に対する調査と誠実な対応の要請を続ける他、会社についても今回の問題について「組織としてのありよう」を検証し、最終号で公表するとしている。
2019/1/31 8人目の被害者が毎日新聞に実名手記を発表。タイトルは「性犯罪の温床を作り出したデイズジャパンの労働環境」で、編集部での過酷な長時間労働やハラスメントが蔓延していた実態を詳述し、広河氏の性暴力が永年隠蔽されてきた背景を分析している。すなわち会社ぐるみで許容されてきたパワハラ体質と性暴力は密接に関係していた訳である。
http://mainichi.jp/articles/20190131/k00/00m/040/128000c
同日 「週刊文春」2019年2月7日号は、元アルバイトの女性による新たな性暴力被害の証言を掲載。広河氏からの依頼で海外取材に同行した際、現地で部屋が一つしか用意されておらず、取材先の男性スタッフ達から性交渉の依頼があること(真実か?)を伝えられた上で「彼らとセックスするか、僕と一つになるか、どっちか」と迫られたと言う。それから2週間は「悪夢のような日々」であったと語っている。
2019/2/15 DAYS JAPAN社、最終号の発売を1ヶ月延期すると発表。当初2月20日発売の予定であったが、広河氏によるセクハラ・パワハラ行為についての会社としての検証記事を掲載するとしていた。発売を3月20日に延期し、3・4月合併号とする (7*) 。
この間の編集部、取締役会、検証委員会の変遷に関しては注8*で触れているが、何れにしても、雑誌の最終号で今回の事件の検証を担うべき中心メンバーを巡る混乱振りは素人目にも明らかである。私自身、ジャーナリスム業界や出版界を殆ど知らないので、次々出て来る個人名にコメントのしようも無いが、雑誌を支えてきた人々が受けた衝撃の大きさがその混乱に現れているのだろう。
次の記事では、本事件の「検証」をめざし、3月中旬に刊行された3・4月合併号(最終号)を紹介し、重要と思われる幾つかの論点(広河氏個人、雑誌デイズジャパンは説明責任を果たしたか?個人及び会社の検証は十分に進んだか?広河氏、或はデイズジャパンの「実績」は全否定されるべきか?)について一読者の観点からコメント・感想を述べてみたい。
参考記事
https://wezz-y.com/archives/62586
https://abematimes.com/posts/5471992
https://businessinsider.jp/post-182763
https://biz-journal.jp/2019/02/post_26520.html
https://buzzfeed.com/jp/akikokobayashi/daysjapan
DAYS JAPAN 2019年2月号、3/4月合併号(最終号)
(2) 注1*~8*
*1広河隆一氏 人権派フォトジャーナリストとして知られ「被害者の立場に立って」パレスチナ、チェルノブイリ、福島等についての取材・報道に取り組み、2004年より15年にわたり報道写真誌「DAYS JAPAN」の編集長や発行人をつとめた。75歳。
*2 DAYS JAPAN 一時期定期購読者数は一万人を超えたとも言われる。また、世界的な報道写真賞でもあるDAYS 国際フォトジャーナリズム大賞を主催し、ここ何年かは世界の報道写真家に多くの(副)賞を選考・贈呈している。各地でこの写真誌の「読者会」なるものも結成され、写真展を企画するなど草の根的な支援層も日本各地にあったもようである。
*3性暴力・セクハラ被害の証言 証言の詳しい内容は、元記事を参照されたいが、例えば、2007年頃編集部でアルバイトをしていたジャーナリスト志望の女子大生:広河氏から「僕が写真を教えてあげる」と都内のホテルに誘われ、セックスに持ち込まれた。かねてより編集部内での師の権力を目の当たりにしており「逆らってはいけない人」との思いがあったため断れなかった。その後も業務で叱責されたあとに性交を強要されるなどしたが、立場的に「ここで見放されたらジャーナリストの道は開けない」と思い込み応じてしまった。2008年頃編集部で働いていた当時18歳の女子大生:氏からアシスタントの話をもちかけられたが「アシスタントになるなら一心同体にならないといけないから、体の関係ももたないといけない」と言われ、ジャーナリストの夢のためにセックスに応じた。女性は「断ったら弟子失格の烙印を押されるのではないか」との思いからその後も関係は続いた。その結果。女性は「中くらいのうつ」と診断され、大学を休学、DAYS JAPAN編集部からも離れた。その後写真から離れた生活を送っていたが、東日本大震災の際に広河氏から「アシスタントとして一緒に来ないか」との連絡を受け、夢を諦めきれずに同行。しかしその出張先でも、高熱と薬の副作用で意識朦朧の中、性交を強要された。他にもDAYS JAPAN に関わっていた複数の女性が、「写真を教える」という名目のもとヌード撮影を強要されたり、肉体関係をもつよう誘われたりした過去を暴露している。編集部内で、広河氏によりその圧倒的立場を利用したセクハラが多くの女性に対し長期間行われていたという許し難い恥ずべき状況があったことは疑う余地はないようである。
文春の直撃取材に対し、広河氏自身は女性達との肉体関係は認めつつも「望まない人間をホテルには連れて行かない」、「僕に魅力を感じたり憧れたりしたのであって職を利用したつもりはない(良く聞く論法!)」と反論・弁明している。
*4 広川氏自身からのコメント(全文写し)
週刊文春2019年1月3日・10日号に私に関する記事が掲載されました。
この記事に関して、私は、その当時、取材に応じられた方々の気持ちに気がつくことが出来ず、傷つけたという認識に欠けていました。私の向き合い方が不実であったため、このように傷つけることになった方々に対して、心からお詫び致します。
なお、今回の報道により、私は、株式会社デイズジャパンの代表取締役を解任され、取締役の地位も解任されたこと、またNPO法人沖縄・球美の里についても、名誉理事長を解任されたことをご報告いたします。
2018年12月26日 広河隆一
セクハラ行為自体についての言及・謝罪は全く無いまま、直撃取材時の反論から唐突にお詫びに転じているがその理由は違和感がある。果たして「向き合い方」の問題だろうか?「気がついていなかったから」あるいは「傷つけたという認識はなかったので」行為自体は仕方が無かったとでも言っているように聞こえる(轢き逃げと同じ?)。
*5 デイズジャパン社からのコメント(コメント全文)
読者のみなさまへ
週刊文春2019年1月3日・10日号に掲載された広河隆一氏の記事に関して
週刊文春2019年1月3日・10日号に掲載された広河隆一氏の記事に関して、本年12月24日、広河隆一氏(以下「広河氏」)から取材を受けたとの報告があり、弊社としては、直ちに広河氏に対して、聞き取りを行いました。
その結果、広河氏としては、その当時、取材に応じられた方々の気持ちに気がつくことが出来ず、傷つけたとの認識を持っていなかったこと、傷つけたとの認識を持ち得ないまま今日に至ってしまったことを確認しました。
長年にわたってDAYS JAPAN誌の編集長・発行人としてかかわってきた広河氏が、被害者の方々の尊厳を傷つけてしまったことに対して、弊社として、心からお詫び申し上げます。
弊社としては、DAYS JAPANが標榜する理念に照らしても、極めて深刻な事態だと認識し、こうした事態を踏まえ、昨日、臨時取締役会を開催し、広河氏を代表取締役から解任し、また、臨時株主総会を開催し、取締役からも解任いたしました。広河氏との関係も清算中です。
弊社として、広河氏の言説を看過するわけにはいかず、これに与する立場ではないことも鮮明にいたします。
広河氏が、自ら本件について誠実な対応を取ることを求めるとともに、弊社としても、弊社の存在意義をふまえ、最後までDAYS JAPANの刊行に取り組む所存です。
末尾ながら、読者の皆様を始め、広河氏とともに活動してきた方々の信頼を失わせる事態となってしまったこと、また関係者の方々に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます。
2018年12月26日 株式会社デイズジャパン
広河氏からのコメントと同じくハラスメンと行為自体についての言及は無い。自体の深刻さは指摘しているものの「なぜ深刻なのか」についてもはっきりしない。今後の本人、及び雑誌としての誠実な対応は最低限の義務であり、多くの人々が関心を持ち続けるであろう。
6*(2回目のコメント全文)
みなさまへ
週刊文春2019年1月3日・10日号の取材に応じられた方々をはじめ、被害にあわれた方々とご家族・関係者の方々、また読者の皆様へ深くお詫び申し上げます。
本年12月26日付の弊社の声明及び広河氏のコメントが発表されて以降、多くの方々からご意見をいただきました。なかには、弊社サイトに掲載した広河氏のコメントについて、「デイズジャパンはあのコメントで良いと思っているのか」と言う厳しいご指摘もありました。
弊社は、本年12月26日付の声明でも明らかにしたように、広河氏から記事の件について報告を受けて以降、継続的に広河氏に対して聞き取りを行っており、声明を発表した後も続けております。聞き取りを通じて、記事で取材に応じられた方々以外にも、同種の件があったことを確認いたしました。
また、弊社においては、今回報じられたような「性暴力」とは別に、(広河氏による?)社員や協力スタッフに対するパワーハラスメントと評価されるべき事態が複数回ありましたが、個別的な対応に留まってきました。
過去のこれらの問題について、社員や協力スタッフから問題提起があったこともありましたが、会社として被害を受けた方の訴えに真摯に対応し、二度とそうした被害が生じないよう全社を挙げて対策をとることをせず、会社として取り組むべきことを取り組まないまま今日に至ってしまいました。
今回の報道を契機として、あまりにも遅すぎましたが、広河氏個人の責任とは別に、弊社としての責任を痛感しているところです。
現在、弊社は、今回の報道を機に就任した弊社代理人を責任者として、広河氏個人の過去の言動による被害実態について調査を行うとともに、広河氏を絶対化させてきた会社の構造・体質についても、役員など関係者への聞き取りなどの調査を行っているところです。
弊社としては、広河氏の解任によって今回の件が終結させられるとは考えておりませんし、そうあってはならないと考えています。広河氏に対しては、これまでの広河氏自身の言動によって被害を受けた方々に誠実に対応することを求め続けていきますし、弊社としても、自らのこの間の組織のありようについて真摯に検証し、弊社雑誌「DAYS JAPAN」の最終号において公表する予定です。
2018年12月31日 株式会社デイズジャパン
7* デイズジャパンは発売延期の理由を、最終号では「検証委員会の報告に加え、人権や差別をテーマに掲げている団体・個人においても不可視化されてしまう女性差別・ハラスメントの問題に取り組み伝えていこう」と考え「最終号の編集委員を、これらの問題に取り組んできた方々へお願いし、発売を1が月延期することで、現在出来ることを見て頂く」ということにしたと述べている。また検証委員会のメンバーとして次の3名も公表している(8*)。委員長 金子雅臣氏(一般社団法人 職場のハラスメント研究所 代表)、委員 上柳敏郎氏(弁護士)、委員 太田啓子氏(弁護士)。
8* 人事・検証体制の混乱
素人が理解するのはかなり困難を伴うが、この経緯をネット情報など
https://bunshun.jp/articles/-/10742
をもとに辿ると大体次のようになりそうである。
1月19日発行の2月号に「編集部の今後の方針と次号について」というメッセージがあるが(内容には後で触れる)、末尾には、DAYS JAPAN編集長 ジョー横溝、編集部 小島亜佳莉、金井良樹 とある。しかしながらほぼ10日後の1月末、ジョー横溝編集長は辞任するが、2月初めの集会で「なぜ15年間みんな黙ってきたのか、掘り起こさないといけないと言ったんですが、それが上に通じず、僕はDAYSを去ることになりました」と語ったと言う。
また「新しい代理人」として2018年末に任命した馬奈木誠太郎弁護士を2週間足らずの2月13日で解任し、次の新しい代理人として、竹内彰志、稲村宥人両弁護士が決まったようである。そして彼らと会社執行部(取締役会?)により、「第三者性を担保した」検証委員会を1月末までに発足させたと言う。検証委員会の委員長には金子雅臣氏(労働ジャーナリストで社団法人「職場のハラスメント研究所」所長)、委員には記述の通り、上柳敏郎氏、太田啓子氏の両弁護士が選ばれた。
今ひとつこの間全く見えないのは会社執行部、即ち取締役会の構成である。広河氏の解任後代表取締役(及びDAYS発行人)に選ばれたのは川島進氏で、DAYS創刊号からアートディレクターをつとめ、デイズジャパン設立当初からの取締役・株主でもある。二人の付き合いは30年以上前に遡り、講談社時代 (1988-90) のDAYS JAPANでともに仕事をした後も広河氏の多くの著書で、装丁やデザインを担当、氏とは盟友ともいえる間柄らしい。最終号の発行責任者はこの川島進氏であった。もう一人の取締役は広河氏の妻で(2018年11月就任)大手出版社の編集者で広河氏の著作の編集も担当しているらしい。即ち 公私とも極めて関係の深い人物である。
3人目の取締役は、先述の講談社「DAYS JAPAN」で編集長をつとめた土屋右二氏で、やはりデイズジャパン設立時からの取締役である。「広河君のことは同士だと思っていた」らしいが性暴力の報道を受け決別を決意、デイズジャパンには1月には取締役辞任の通知を出したと言う。川島氏からは「取締役は3人必要なので辞任は認められない」と言われたが、もうデイズジャパンには一切関わらないと話したという(多分1月末時点)。